| アベノミクスの失敗、異次元緩和の失敗 H27.12.30 安倍政権が発足し3年、アベノミクスが失敗に終わりアベノリスクになってしまいました。 日銀の異次元緩和が2年9カ月を経過し、まったく何の効果も出せていません。 その間、消費税率が5%から8%に引き上げられ、国民の生活は苦しくなりました。 アベノミクスの失敗、異次元緩和の失敗、失敗した理由はハッキリしています。 過去の成長時代の金融政策が現時代に通用しなかったことです。 日本にインフレを目標にしたリフレ策を奨めたのは米国のノーベル賞経済学者ポール・クルーグマンです。 日銀が国債を大量に買ってマネーを増刷すれば、それが投資と需要の増加を生んでデフレから脱却でき、日本経済は成長に向かうという考え方です。 リフレ派の黒田日銀は金融機関が保有する国債を年間で80兆円も買取ってきました。 そのお金が市中に回れば資金の循環で景気がよくなっていくのでしょうが、 金融機関に入ったお金は日銀の当座預金にたまったままで、市中には回っていません。 GDPは、三面等価の原則で、生産、分配(所得)、支出の三面から国内総生産(GDP)は同じ値になり、支出面から見たGDPは次式によります。 「民間消費+住宅+企業の設備投資+在庫増+政府消費+公共投資+輸出ー輸入」 民間消費が約60%を占め、経済成長の重要なポイントになります。 その他は、①住宅は減少、②企業の設備投資は抑制、③在庫増はあっても軽微、④政府消費、 ⑤公共投資は予算によりほぼ一定、⑥輸出-輸入は近年は貿易赤字になっています。 つまり、経済成長させるためには、民間消費を増やすことになります。 政府・日銀は、目的と手段が間違っているのです。 戦略と戦術の問題と言ってもよいでしょう。戦略は経済成長、戦術はたくさんあります。 リフレ論による金融政策は、戦術の中の一つにすぎません。 サラーリマンの平均年収 次のグラフはサラリーマンの平均年収の推移です。 過去の推移をみることで賃金動向を大まかに把握することができます。 年収推移のグラフ http://nensyu-labo.com/heikin_suii.htm 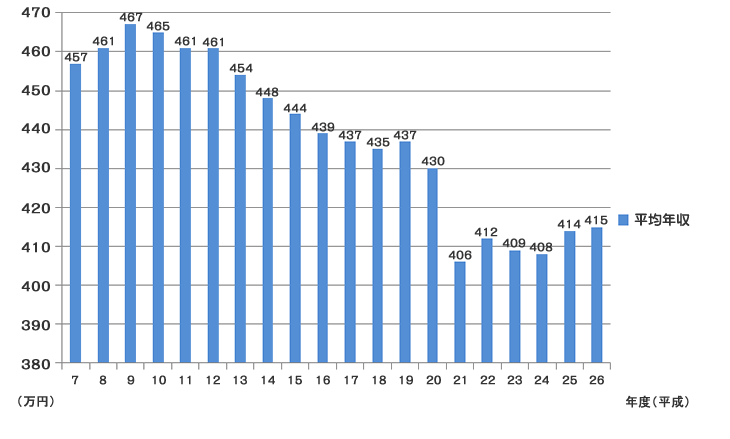 統計元:国税庁 平成26年 民間給与実態統計調査結果 民間企業で働くサラリーマンや役員、パート従業員の平成26年の平均年収は415万円です。 若干の上昇を見せた平成25年でしたが、平成26年は昨年とほぼ変わらず415万円を記録しています。 国税庁「平成26年分 民間給与実態統計調査」によると、 平成26年(平成26年12月31日現在)の平均年収は415万円で、 昨年の408万円に比べ+0.1万円(+0.2%)の増加となりました。 男女別平均では、男性は514万円で前年比+3.1万円(+0.6%)の増加、 女性平均は272万円で+0.7万円(+0.2%)の増加を記録しています。 また、1年を通じて勤務した給与所得者に支払われた給与の総額は197兆4,043億円で、 前年に比べ+2.7%の増加となっています。 平成21年から平均年収は、ほぼ横ばいですが、消費税率のアップや社会保険料率のアップにより 可処分所得は減少しているものと見られます。 非正規社員が4割に 厚生労働省が発表した就業形態の多様化に関する調査によると、派遣など正社員以外の労働者の割合が、平成26年10月時点で4割に達しました。 高齢者の再雇用やパートが増えたことが要因のようです。 空いている時間を有効に使いたい人や、定年後も仕事に生きがいを持ちたい人ばかりではありません。 育児・介護との両立や老後の経済的不安から、やむを得ず非正規社員を選択している人が少なくないでしょう。 アベノミクスで雇用が増えたといわれますが、正社員の数は減っているのです。 この調査結果から、正社員の1カ月の賃金は20万~30万円未満の人が約3割と最も多く、 非正規社員では20万円未満が圧倒的に多く、派遣や契約社員の5割、パートの9割を超える状態とか。 安倍政権は平成27年9月に改正労働者派遣法を成立させ、企業はますます「コスト削減のため」 非正規社員を活用していくと言っています。 引用 --------------------------------------------------------- サラリーマンの平均年収。正社員と派遣ではこんなに違う。 http://raorsh.com/seisyain 正規雇用者と非正規雇用者は、平均年収で大きく異なります。 厚生労働省「民間給与実態調査」によれば、 https://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/minkan2014/minkan.htm ?正規雇用者: 477万7千円 ?非正規雇用者: 169万7千円 と、なんと300万円の差が開いています。 ただ、非正規雇用は派遣社員、契約社員だけではなくフルタイムではないパートタイマーなども含まれている為、一概には比較できません。 そこで、より比較できるのは男性に限定した場合でしょう。 女性にくらべるとパートタイマーが少ないと推定できるためです。 男女別の平均年収は以下の通りです。 ?正規雇用者(男性): 532万3千円 ?正規雇用者(女性): 359万3千円 ?非正規雇用者(男性): 222万3千円 ?非正規雇用者(女性): 147万5千円 男性限定でみた場合においても、やはり300万円程の差がありました。 やはりこれほど差があるということでしょう。 平均20万円でも年収は240万円ですから、非正規雇用の男性は平均的にはそれ以下となってしまっているというのが現実です。 通常の正社員は、会社に入った後で、様々な仕事を経験し、力をつけていきます。 そして、仕事ができるようになり、出世し給料もあがっていきます。 しかし、非正規雇用者は長くは働くことができずに、経験して仕事を深くまで身に付けることができずにいることになってしまいます。 その為、年収も若い頃と同じままであり、増えていきません。 --------------------------------------------------------- 非正規社員の待遇改善が最重要 経済成長と人口の増減の関係は密接に関係しているものと思われます。 日本経済を成長させるためには、 ①平均年収を増やし<可処分所得を増加させること。 ②人口を増やし<消費を増加させること。にあります。 そこで問題になるのは非正規社員の待遇改善です。 個々には、いろいろな事情で非正規にならざるを得ないのですが、非正規社員が4割に達し、今後さらに増加していくものと推測できます。 この4割に達する非正規社員の年収を見てみると、結婚して子供を産んで育てていけるか考えたとき、経済的に成り立ちません。 非正規社員の待遇改善は、政府はもとより、企業の社会的責任において実効していかなければなりません。 20年先の生産人口を確保していくことにも必ず必要なことです。 日本の経済を成長させ、企業を存続させていくにも、今必要な対策でしょう。 企業は、利益を蓄積するだけでなく、従業員への還元を考えなければなりません。 政府は、公務員の年収が、民間の正規社員の年収をはるかに上回っていることを考えて、 例えば、民間の正規社員の年収ベースまで賃金カットし、非正規社員への待遇改善のための所得移転も考慮していかなければ、日本の明るい将来はないかもしれません。 個人的には、人を商品扱いにしている派遣法には違和感をもっています。 このままでは、いずれ、非正規社員の比率が5割を超える事態になっていくことでしょう。 一部の業界では、正社員は少なく、大多数は非正規社員で構成されているところもあるようです。 しかし、企業の存続、ノウハウの蓄積等を考えたら、それでよいのか疑問に思えます。 最近思うことは、大企業が目先の利益だけを追いかけ、海外進出したりして、結果企業の存続を危機に陥れてところが多く見受けられるのが残念です。 引用 --------------------------------------------------------- 植草一秀の『知られざる真実』2015年11月17日 (火) 景気後退に逆戻りしてしまった日本経済 http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2015/11/post-fd27.html 11月16日、2015年7-9月期のGDP統計が発表された。 実質経済成長率は年率換算で-0.8%のマイナス成長となった。 4-6月期に続いて2四半期連続のマイナス成長となった。 米国の定義では、2四半期連続のマイナス経済成長に陥った場合、「リセッション=景気後退」としている。 日本経済は、再び不況に戻ってしまった。 日本経済は2014年に不況に突入している。 2014年4-6月期、7-9月期にマイナス成長に陥った。 昨年10-12月期、本年1-3月期にはプラス成長を記録したが、その後の4-6月期、 7-9月期が再び2四半期連続のマイナス成長に陥ったわけだ。 年率換算の経済成長率は以下のように推移している。 2014年4-6月期 -7.7% 2014年7-9月期 -1.1% 2014年10-12月期 +1.2% 2015年1-3月期 +4.6% 2015年4-6月期 -0.7% 2015年7-9月期 -0.8% そして、2014年度の実質経済成長率は-0.9%だった。 メディアは「アベノミクス」を絶賛し続けてきたが、アベノミクスの実績は明らかに落第点なのである。 2012年11月14日は金融市場の変節点である。 この日、野田佳彦氏と安倍晋三氏による党首討論が行われた。 この日を境に金融市場が流れを変えた。 円安、株高が進行し、アベノミクスが絶賛された。 1ドル=78円、日経平均株価8664円が、半年後の2013年5月22日に1ドル=103円、 日経平均株価15627円に上昇した。 この相場変動で第二次安倍政権が軌道に乗り、3年間に及ぶ長期政権に転じてしまった。 円安が進行した理由は、アベノミクスの第一の施策である金融緩和策強化が一因ではあったが、主因は米国長期金利の上昇だった。 米国10年国債利回りは2012年7月に1.38%の最低値を記録したのち、上昇トレンドに転じた。 この米金利上昇こそ、円安=ドル高進行の主因だった。 そして、為替レート変動に連動した推移を示してきた日本株価が円安に連動して跳ね上がった。 この金融変動のために第2次安倍政権の支持率が高まり、2013年7月参院選での与党勝利をもたらし、安倍独裁政治を招いてしまったのである。 アベノミクスは金融緩和、財政出動、成長戦略を三本柱とするものだとされた。 政権発足当初は、金融緩和政策強化の方針が示されるとともに、13兆円の補正予算が編成され、この財政金融政策の発動が日本株価上昇をもたらしたとも言える。 前任の野田義彦政権が財務省主導の超緊縮財政政策を実施していたため、日本株価は理論的妥当値よりもはるかに低位に押し下げられていた。 この安くなり過ぎていた株価が財政政策スタンスの修正により、適正な水準に回帰し始めた。 このことが、株価急騰の背景であり、安倍政権はその幸運をそっくり手中に収めたのである。 しかし、財政政策の方針は2014年度に180度転覆された。 消費税大増税が強行されたのである。 その結果、日本経済は大不況に陥った。 このことが、2014年4-6月期から7-9月期の2四半期連続のマイナス成長にくっきりと表れたのである。 窮地に追い込まれた安倍政権は、2014年末に、消費税再増税延期の方針を決定した。 そこに、原油価格暴落という幸運が日本経済に提供された。 日本経済は奈落に転落することを免れて、緩やかな景気改善の道筋に入りかけた。 しかしながら、2015年4-6月期、7-9月期のGDP統計が示すように、日本経済は再び不況に逆戻りしてしまった。 安倍政権の経済政策には根本的な誤り、構造的な欠陥がある。 この欠陥を是正しない限り、日本経済の本格浮上はあり得ない。 株価は上昇したが、日本経済は浮上しない。 そのメカニズムを解明しなければならない。 --------------------------------------------------------- |